「高額な医療費を払った年があったのに、確定申告で医療費控除を入れ忘れてしまった…」
「もう何年も前のことだから、税金は戻ってこないだろう」
もしあなたがそう考えているなら、それは大きな間違いです!
実は、医療費控除は確定申告の期限を過ぎても最大5年間さかのぼって申請でき、払いすぎた税金(所得税・住民税)を取り戻すことができます。この手続きを「還付申告」といい、知っている人だけが得をする制度です。
この記事では、医療費控除を過去にさかのぼって申告するための正しい手順と、税金を取り戻すために知っておくべき必須知識を、税金の知識がない方でも完全に理解できるように分かりやすく解説します。
- 医療費控除を最大5年間さかのぼって申告できる仕組み(還付申告と更正の請求の違い)。
- 過去分の申告に必要な具体的な書類(医療費通知書、源泉徴収票など)と準備手順。
- 控除額の正確な計算方法と、家族で申告する際の還付金を増やすコツ。
- 通院費や市販薬など、控除対象になる費用・ならない費用の明確な判断基準。
医療費控除は5年間さかのぼって申告できる!その仕組みと期間
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得からその分を差し引き(控除し)、結果として税金が安くなる制度です。
たとえ申告期限(通常翌年の3月15日)を過ぎていても、「還付申告(かんぷしんこく)」という特別な手続きで、過去にさかのぼって申請が可能です。
還付申告の期限と対象期間
還付申告は、その年分の翌年1月1日から5年間提出できます。
たとえば、2025年に申告を行う場合、2020年1月1日から12月31日に支払った医療費までさかのぼって対象となります。5年を過ぎてしまうと、税金を取り戻す権利は失効してしまうため、心当たりのある方は、今すぐ過去の領収書をチェックしましょう。
申告方法の使い分け:「還付申告」と「更正の請求」
過去の申告内容を修正する場合、状況に応じて2つの手続きを使い分けます。
| 手続き名 | 目的と対象者 | 期限 |
| 還付申告 | 確定申告をしていなかった年の税金を取り戻す | 5年以内 |
| 更正の請求 | 確定申告はしたが、医療費控除の適用を入れ忘れた年を修正する | 5年以内 |
どちらの手続きも、提出先は最寄りの税務署、または国税庁のe-Tax(オンライン)でOKです。
医療費控除の基本をおさらい!控除額の計算ルール
まず、医療費控除でいくら控除されるのか、その基本的なルールを確認しましょう。
医療費控除の具体的な計算方法(文字化け完全対策版)
以前のリライト記事でご指摘いただいた計算部分を、標準的な文章で以下のように記述します。
基本の計算式
控除額 は以下の要素で計算します。
控除額 = (実際に支払った医療費の合計額) – (保険金などで補填された金額) – (差し引く金額)
差し引く金額(足切りライン)のルール
上の計算式にある「差し引く金額」は、原則として10万円ですが、総所得金額等によって以下の特例が適用されます。
| 総所得金額等 | 差し引く金額(足切りライン) |
| 200万円以上 | 10万円 |
| 200万円未満 | 総所得金額等の5% |
具体的な計算例
年間医療費が30万円、保険金が5万円、総所得金額等が180万円(200万円未満)の場合の計算です。
- 差し引く金額(足切りライン)の計算:総所得金額等(180万円)の5%を計算します。180万円 × 0.05 = 9万円
- 控除額の計算:計算式に当てはめます。30万円 – 5万円 – 9万円 = 16万円
控除額は16万円となり、この金額に所得税率をかけた分が還付されます。

さかのぼり申告の具体的な手順と必要書類
過去の医療費をさかのぼって申告する手続きは、実は通常の確定申告とほぼ同じです。e-Taxを利用すれば、自宅から全ての手続きを完了できます。
過去分を申告するために、まずは支払いの証拠となる資料を年度別に整理しましょう。
| 必要な資料 | 備考 |
| 医療費の領収書 | 病院、薬局などで受け取ったもの。提出は不要だが、5年間保管が必要。 |
| 医療費通知書 | 健康保険組合などから送られる「医療費のお知らせ」。これが最も便利で、明細書作成時に利用可能。 |
| 源泉徴収票 | 申告対象年(過去分)の源泉徴収票。紛失時は勤務先に再発行を依頼。 |
【重要】領収書がなくても大丈夫!
2017年分以降の申告では、医療費通知書があれば、個別の領収書の提出は原則不要です。また、領収書を紛失した場合でも、医療費通知書やクレジットカード明細などで代用できるケースがあります。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成します。
- 作成コーナーで「過去の年分の申告書を作成」を選択し、申告したい年分を選びます。
- 「医療費控除」の項目で、医療費通知書のデータを活用するか、領収書に基づき医療機関ごとに支払額と補填額を入力します。
- 明細書を作成したら、その控えを印刷し、根拠となる領収書と一緒に5年間大切に保管しましょう。
e-Taxの作成コーナーでは、過去5年分の申告書を簡単に作成できます。マイナンバーカードとスマートフォン(またはカードリーダー)があれば、書類の郵送も不要で、還付も早くなります。
医療費控除の明細書と源泉徴収票の情報に基づき、申告書(還付申告書または更正の請求書)を作成し、以下のいずれかの方法で提出します。
- e-Tax(オンライン提出)
- 税務署の窓口に持参
- 税務署に郵送(「確定申告書在中」と記載)
提出後、通常1か月から1か月半ほどで、指定した金融機関の口座に還付金が振り込まれます。
迷いやすい!控除対象になる費用・ならない費用
医療費控除の対象となる費用は「治療を目的とした支出」です。ここでは、特に読者が判断に迷いやすい費用をまとめました。
| 分類 | 控除対象となる費用 | 控除対象外となる費用 |
| 治療 | 病院・歯科医院の治療費、不妊治療費、出産費用 | 美容目的の整形・歯列矯正 |
| 予防・健康 | 医師の指示による人間ドック後の再検査費用 | 健康診断、人間ドック、予防接種 |
| 医薬品 | 医師の処方箋による薬、治療を目的とした市販薬 | サプリメント、ビタミン剤(セルフメディケーション税制の対象になる場合あり) |
| 移動費 | 通院のための公共交通機関(電車・バス)の運賃 | 自家用車のガソリン代、駐車場代 |
| その他 | 医師の指示によるマッサージ・はりきゅう | 単なる疲労回復・慰安目的のマッサージ・整体 |

領収書がない通院費の申告には、この5点を記録したメモが必須だよ!
1.利用した日: 通院した年月日
2.利用した交通機関: 電車、バス、タクシーなど
3.利用区間と経路: 例:JR横須賀駅から汐入駅
4.運賃: 片道または往復の料金
5.通院の目的: 病名や受診した医療機関名
スムーズな申告のために、漏れなく記録しておきましょう!
申告で最大限得する!3つの重要チェックポイント
せっかく過去にさかのぼって還付申告をするなら、戻ってくる税金を最大限にするための重要なポイントを押さえておきましょう。この3点をチェックするだけで、還付額が変わってくる可能性があります。


1. 制度の選択が重要!医療費控除 vs. セルフメディケーション税制
医療費の控除制度には、一般的な「医療費控除」の他に、特定の市販薬の購入費を対象とする「セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)」があります。
しかし、この二つの制度は同じ年に併用できません。どちらか一方を選択する必要があるため、ご家庭の支出状況に応じて有利な方を選ぶことが非常に重要です。
| 比較ポイント | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
| 対象となる支出 | 病院・診療所の治療費、薬代、通院費などすべての医療費 | 厚生労働省が定める特定のOTC医薬品(市販薬)の購入費 |
| 控除を受けられる条件 | 年間の医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えること | 年間の対象市販薬購入費が12,000円を超えること |
| 控除額の計算 | 支出合計から保険金と足切りライン(10万円など)を引いた額 | 支出合計から12,000円を引いた額(上限88,000円) |
| 向いている家庭 | 入院、手術、出産などで医療費が高額になった家庭 | 病院に行く機会は少ないが、市販薬の購入が多い家庭 |
賢く選択するためのアドバイス
「医療費控除」は、控除額の計算時に足切りライン(原則10万円)があるため、年間の医療費がこのラインを大きく超える場合は、通常こちらが有利です。一方で、市販薬の購入だけで12,000円を超えていれば、「セルフメディケーション税制」の方が少額から控除を受けられるメリットがあります。
迷ったら両方の制度で計算してみて、より還付額が多くなる方を選びましょう。
2. 家族の医療費は「所得が高い人」がまとめて申告する
医療費控除は、「生計を一にする家族(同一生計親族)」全員分の医療費を合算して、その家族のうち誰か一人が代表で申告できます。この時、所得の高い人が申告するのがおすすめです。
ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りをしている別居の親族なども含まれます。
なぜ、「所得が高い人」が申告するのがおすすめかというと、日本の所得税が「累進課税制度」を採用しているためです。
控除額(所得から差し引く金額)は誰が申告しても変わりませんが、税率が高い人が控除を受ける方が、最終的に差し引かれる税金の額(還付金)が大きくなります。
効率的な申告のコツ
家族の中で、最も所得が高く、所得税率が高い人が医療費の総額をまとめて申告することで、世帯全体で最大限の還付金を受け取ることができます。申告前に必ず家族の源泉徴収票を確認し、誰が申告するか話し合いましょう。
3. 過去の申告書類の紛失時は税務署に依頼できる
過去にさかのぼって申告(還付申告・更正の請求)を行う際、申告対象の年(過去分)の書類が必要になりますが、控えや源泉徴収票を紛失しているケースは少なくありません。



「書類がないから諦めるしかない」と考える必要はありません。
紛失した過去の申告書類や源泉徴収票は、以下の方法で再発行や確認が可能です。
- 過去の「確定申告書」の控えが必要な場合:税務署に対して「保有個人情報開示請求」や「閲覧請求」を行うことで、過去の申告書の写しや内容を確認できます。
- 過去の「源泉徴収票」が必要な場合:原則として、勤めていた(いる)会社の経理担当者に連絡して、再発行を依頼する必要があります。
特に、勤務先の情報や過去の所得金額がわからないと正確な申告ができません。手続きを始める前に、まずは税務署や過去の勤務先に相談してみましょう。
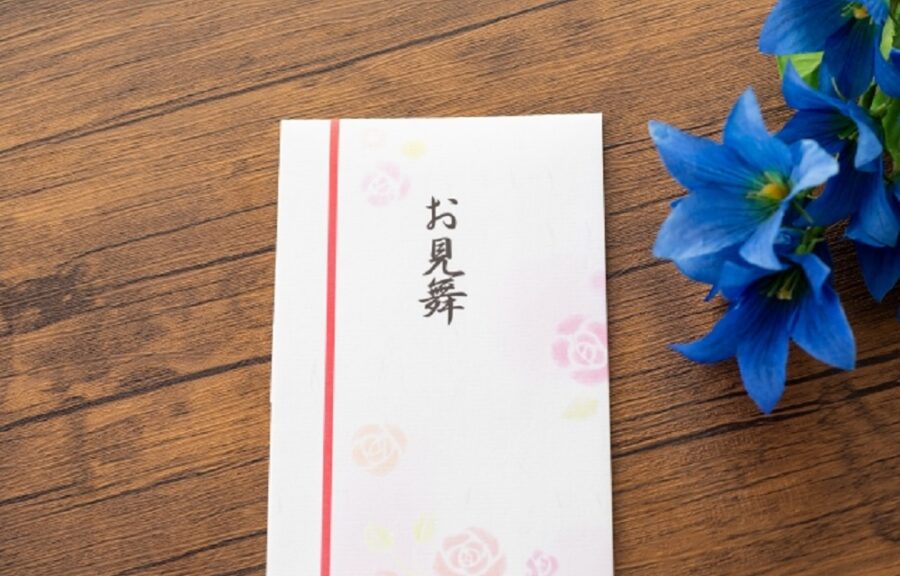
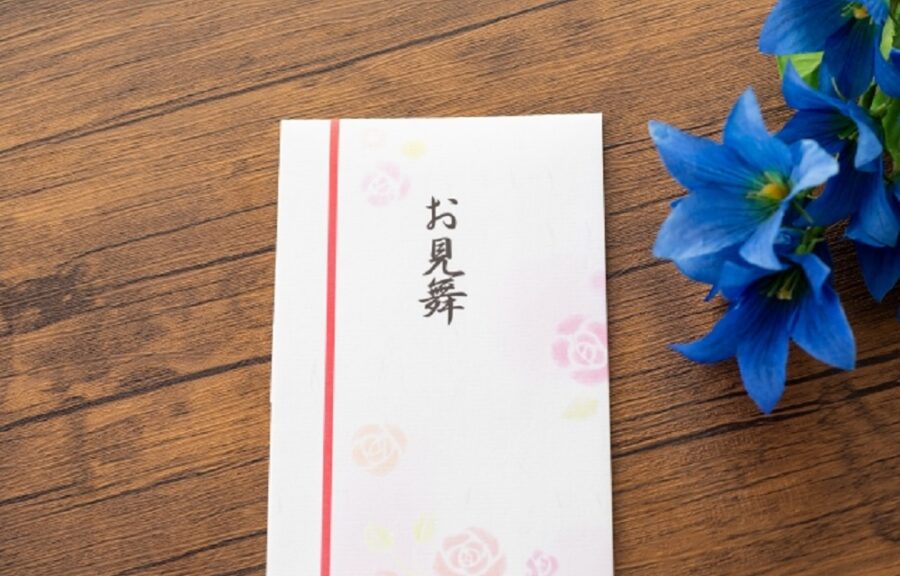
まとめ:医療費控除の還付申告は「やらなきゃ損」
医療費控除の申告を忘れてしまっても、過去5年間は「還付申告」という形で税金を取り戻せる、非常に価値の高い制度です。
申告に必要な手続きは、国税庁のe-Taxを使えば自宅から簡単に、しかも郵送や窓口の待ち時間なしで完結できます。
特に、過去に出産、手術、不妊治療など、高額な医療費がかかった年がある方は、5年の期限が切れる前に領収書や医療費通知書を確認してみてください。
「もしかしたら数万円、数十万円戻ってくるかも」と思ったら、すぐに手続きを始めることを強くおすすめします。
医療費控除をさかのぼって申告する際の「よくある質問(FAQ)」
過去分の医療費控除の手続きを進める際、多くの方が抱く疑問や不安をまとめました。このFAQを確認して、疑問や不安を解消し、安心して還付申告を完了させましょう。
- 領収書をなくしてしまった場合はどうすればいい?
-
領収書をなくした場合でも、医療機関で再発行してもらえるケースがあります。また、健康保険組合が発行する「医療費通知書」やクレジットカードの利用明細で支払いを証明できる場合もあります。再発行が難しい場合は、支出をできる限り正確に記録したメモを添えると良いでしょう。
- 既に確定申告を済ませている場合でも修正できる?
-
はい、可能です。既に申告を終えている場合は「更正の請求」という手続きで修正できます。申告後5年以内であれば、医療費控除を追加して再計算が可能です。税務署に更正請求書を提出するか、e-Taxから手続きを行いましょう。
- 扶養家族の医療費は誰が申告するの?
-
「生計を一にしている家族」の医療費であれば、誰が支払っても申告できます。たとえば、妻が支払った医療費を夫の名義でまとめて申告することも可能です。一般的には、所得が高い方がまとめて申告すると還付額が大きくなる傾向があります。








